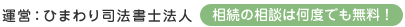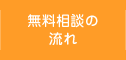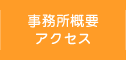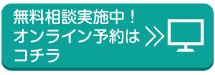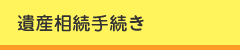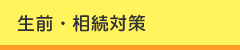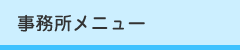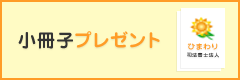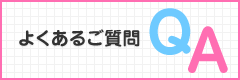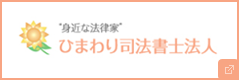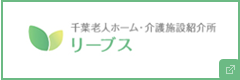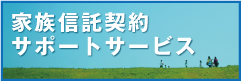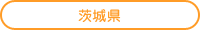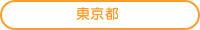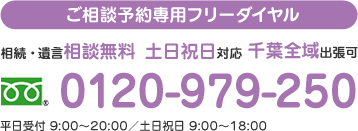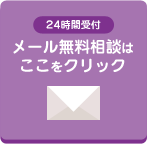【千葉市中央区・相続手続き・Yさん】出産前の子供(胎児)にも相続税は関係するのか?
千葉市にお住まいのYさんよりのご相談です。
Yさんのご主人が急逝してしまい、Yさんとその出産予定のお子様が相続人になってしましました。Yさんより、相続税の申告をしなければならないが、まだ生まれていない子供は相続税の計算上、どう対処すえればよいかとのご相談がございました。
「胎児の相続」
民法上、胎児についてはすでに生まれた者として相続権を認めています。したがって、死産または流産をしない限り、胎児も法定相続人の1人と認められます。
≪胎児≫
出生(生存) → 相続人となる
死産 → 相続人とならない
「相続税法の取り扱い」
①胎児の納税義務
相続開始の時に胎児がいる場合、相続税の申告提出までに生まれていない時は、その胎児はいないものとして各相続人の課税価格の計算を行います。胎児が生まれている場合には、法定相続人の数に含め、遺産に係る基礎控除を計算し、各相続の課税価格、相続税の総額などを計算します。胎児が申告期限までに生まれていないため、法定相続人の数に含めず相続税を計算し、その後胎児が生まれた場合は、遺産に係る基礎控除、相続税の総額などの再計算をすることになります。この場合、胎児であった相続人については通常の相続税の申告を、その他の相続人については更正の請求をそれぞれ行う事になります。
②胎児が出生した場合の提出期限と他の共同相続人の更正の請求
胎児であった相続人の申告書の提出期限は、その者の法定代理人がその胎児の生まれた事を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められており、法定相続人がその胎児に代わって期限後申告書を提出することになっています。相続税の申告期限後、胎児が生きて生まれたことにより相続人に異動が生じた結果、すでに納付してある相続税が過大になった場合、その他の共同相続人は胎児が出生の事実を知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行い、納め過ぎとなった相続税の還付を受けることになります。
③胎児がいる場合の申告期限の延期
申告期限までに生まれていない胎児をすでに生まれたものとみなして課税価格や相続税額を計算した時、相続または遺贈により財産を取得した全ての者の納付すべき相続税額がゼロになり、相続税申告書を提出する義務がなくなる場合があります。このような場合、胎児以外のの相続人が申請すれば、これらの者に係る相続税申告書は、胎児が生まれた日後2ヶ月の範囲内で延期することができます。
≪相続人となる胎児≫
・申告期限後に出生
↓
胎児がいないものとして相続税を計算
↓
出生
↓
法定代理人が胎児が生まれた事を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告
その他の相続人については4ヶ月以内に更正の請求
・申告期限前に出生
↓
通常の相続税の申告
↓
法定代理人が胎児が生まれた事を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告